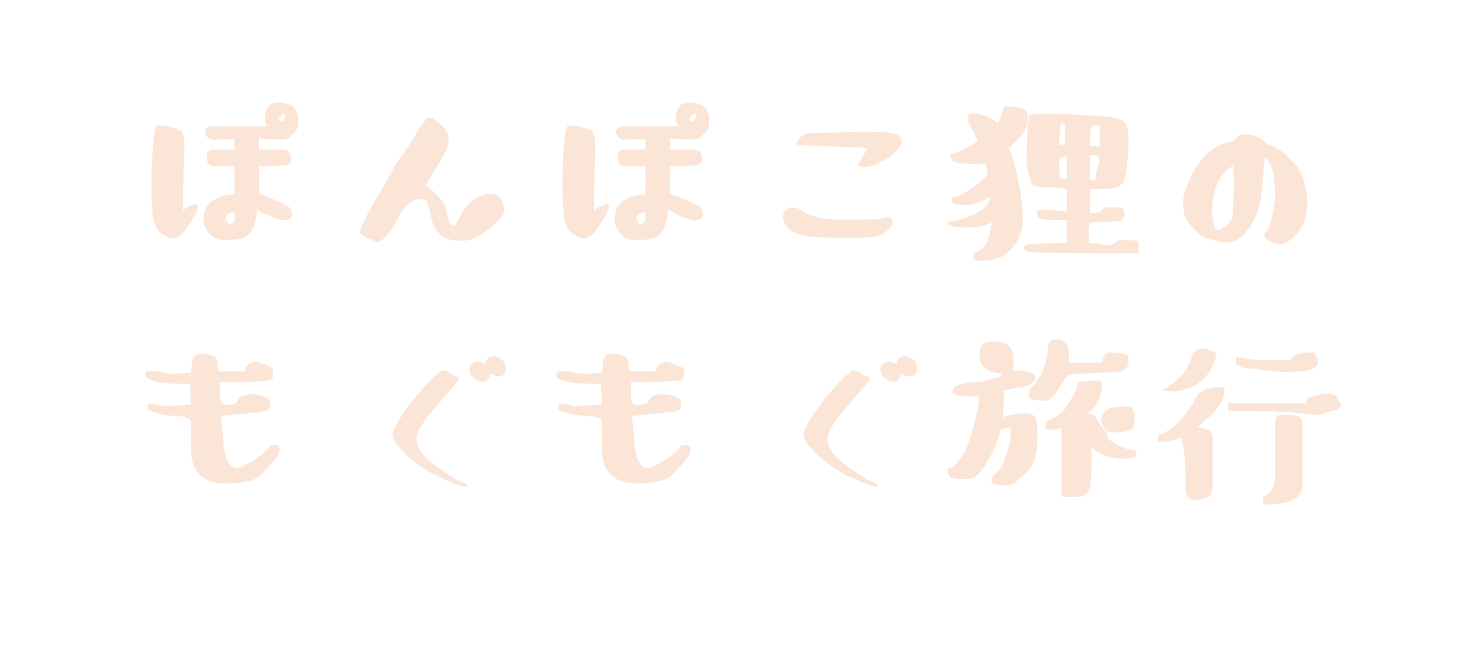武田信玄と所縁の地であり、甲府五山にも数えられる東光寺、そこに諏訪頼重のお墓があります。
諏訪頼重とはどんな人物なのでしょうか。
武田信玄と所縁の地である東光寺になんでお墓があるのかな。
武田信玄と関係があるのかな?
諏訪頼重とは?
享年:26歳
永正13年(1516年)~天文11年(1542年)
諏訪大社を中心とする名門の当主
諏訪頼重は、諏訪大社の神職を務める名門・諏訪氏の第19代当主。
信濃国の戦国大名であると同時に神官でもあり、地域の支配者としての立場も持っていました。
生涯
信濃の有力武将として活躍
戦国時代、信濃国には多くの小領主がひしめいていました。
頼重はその中でも有力な勢力を築いていましたが、隣国の武田信玄との対立が激化していきます。
武田家との戦いと和睦
諏訪家は、諏訪頼重の諏訪頼満(祖父)と諏訪頼隆(父)の時代に武田家と、戦を繰り返しており、反武田派として甲斐国内へ侵攻していたが、1535年(天文4年)に武田信虎(武田信玄の父)と諏訪頼満(祖父)は和睦した。
諏訪頼重は、1540年(天文9年)11月、武田信虎の三女で、信玄の妹だった「禰々(ねね)」と結婚し、武田家と親戚関係になりました。
いわゆる政略結婚だね。
諏訪家の当主として
諏訪頼満(祖父)1539年(天文8年)12月9日が死去したことにより、に家督を継ぐ。
父の頼隆は、1530年5月15日(享禄3年4月18日)に死去してしまっていたんだよ。
武田信玄との戦い、そして敗北
天文10年(1541年)6月。甲斐の国では、武田信虎が駿河に追放され、そのあとを息子の武田晴信(のちの信玄)が継いで国のトップになりました。そして信玄は、本格的に信濃(現在の長野県あたり)への攻め込みを始め、まずは諏訪の地域に侵攻したのです。
そして、天文11年(1542年)諏訪頼重は武田軍に敗れ、捕えられます。
自害へと追い込まれる
天文11年(1542年)、頼重は甲府に護送され、やがて甲府東光寺で自害に追い込まれたとされます。
今なお、東光寺には諏訪頼重の墓があります。
この時、まだ若かった娘(のちの諏訪御料人)は信玄の側室となります。
辞世の句
「おのつから かれはてにけり 草のはの 主あらはこそ 又もむすはめ」
自然のままに、すっかり枯れてしまった草の葉のように、
それを守る主(あるじ)がいれば、また芽を結ぶ(再生する)こともできるだろう。
つまり、草は放っておけば枯れてしまう。けれど、それを世話する人、主(あるじ)がいれば、また芽吹き、命をつなぐことができる。
諏訪家の再興を考えていたのかな?
諏訪家の血族
このため、幼少期や若い頃は「武田勝頼」ではなく「諏訪勝頼」とも呼ばれていました。
武田家の統治
武田氏は信濃を治めるために、地元の有力な家に自分たちの一族を送り込んで、その家の名前や立場を引き継がせることで、うまく仲良くやっていこうとするやり方をしていました。
信玄の四男で、諏訪御料人との子どもだった勝頼は、一時的に諏訪氏の名跡(家名)を継ぐ形で、諏訪家の当主として「諏訪四郎勝頼」と名乗りました。
つまり、形式的に母方の家である諏訪氏の「養子」となったのです。
のちに勝頼は、武田家を継ぐことになります。頼重の血は、武田家の中核に引き継がれていったのです。
諏訪家の血
諏訪家としては、勝頼は正式な家系図では歴代の当主とはされていません。
本来の諏訪家の神職である「大祝(おおほうり)」という重要な役目は、信玄の義理の叔父にあたる諏訪満隣(すわ みつちか)の家系が引き継ぎました。
そしてその子孫たちは、江戸時代には諏訪藩の大名として復活したのです。
ぽんすけのまとめ
信濃の名門・諏訪家のリーダーで、諏訪大社をまもるおうちの19代目!
なんと、武田信玄の妹のダンナさん(=義弟)であり、
さらに!信玄の側室のお父さん(=義父)なんだって。
頼重さんの娘さんが信玄の側室になって、その間に生まれたのが、あの武田勝頼公つまり、頼重さんの血はちゃんと武田家に流れてるんだよ。