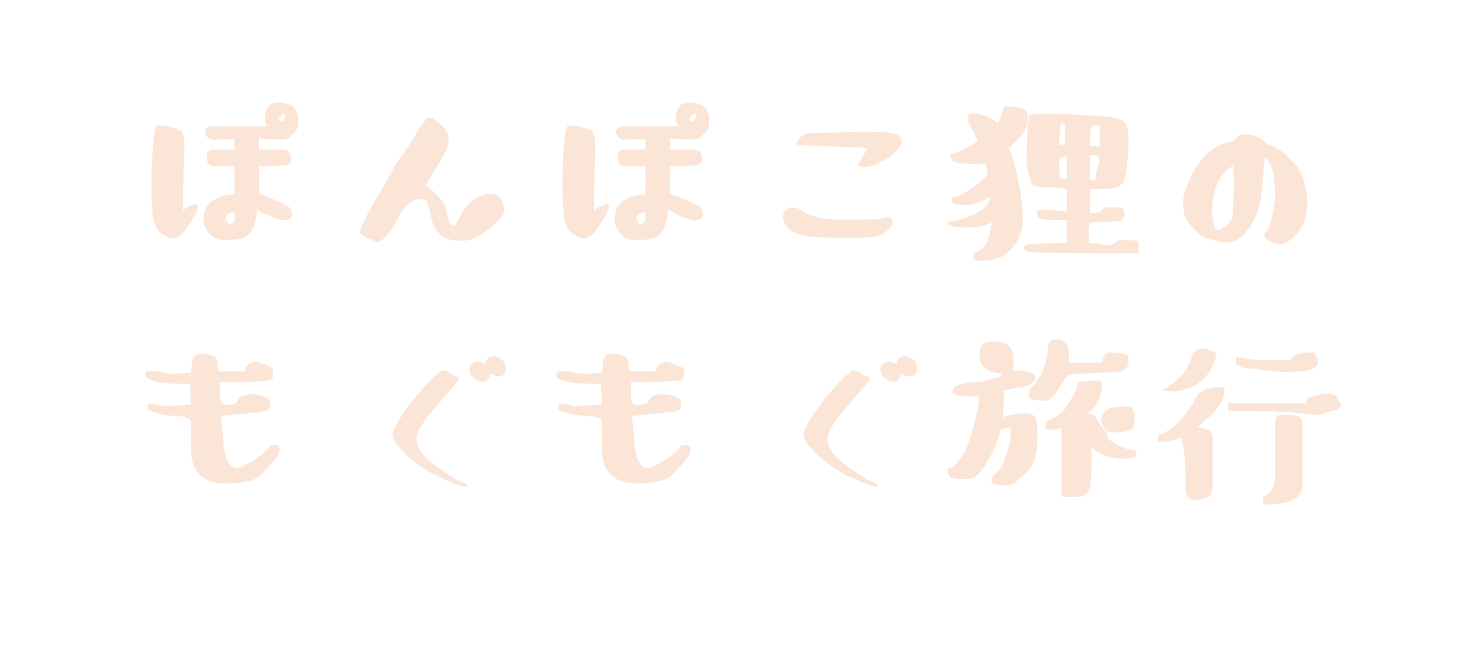東海道五十三次(とうかいどう ごじゅうさんつぎ)ってのはね、
むか〜し江戸時代に、江戸(いまの東京)から京都までを結ぶ東海道っていう大きな道があったんだよ。
その道の途中には、旅人が休んだり泊まったりする場所=宿場(しゅくば)があって、その数がぜんぶで53か所あったんだ。だから“五十三次”っていうんだよ〜!
東海道五十三次 りすと
| 番号 | 宿場名 | 現在の市 |
|---|---|---|
| 1 出発点・江戸 | 日本橋(にほんばし) | 東京都中央区 |
| 2 | 品川宿(しながわしゅく) | 東京都品川区 |
| 3 | 川崎宿(かわさきしゅく) | 神奈川県川崎市川崎区 |
| 4 | 神奈川宿(かながわしゅく) | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 5 | 保土ヶ谷宿(ほどがやしゅく) | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 6 | 戸塚宿(とつかしゅく) | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 7 | 藤沢宿(ふじさわしゅく) | 神奈川県藤沢市 |
| 8 | 平塚宿(ひらつかしゅく) | 神奈川県平塚市 |
| 9 | 大磯宿(おおいそしゅく) | 神奈川県中郡大磯町 |
| 10 | 小田原宿(おだわらしゅく) | 神奈川県小田原市 |
| 11 | 箱根宿(はこねしゅく) | 神奈川県足柄下郡箱根町 |
| 12 | 三島宿(みしましゅく) | 静岡県三島市 |
| 13 | 沼津宿(ぬまづしゅく) | 静岡県沼津市 |
| 14 | 原宿(はらしゅく) | 静岡県沼津市 |
| 15 | 吉原宿(よしわらしゅく) | 静岡県富士市 |
| 16 | 蒲原宿(かんばらしゅく) | 静岡県静岡市清水区 |
| 17 | 由比宿(ゆいしゅく) | 静岡県静岡市清水区 |
| 18 | 興津宿(おきつしゅく) | 静岡県静岡市清水区 |
| 19 | 江尻宿(えじりしゅく) | 静岡県静岡市清水区 |
| 20 | 府中宿(ふちゅうしゅく) | 静岡県静岡市葵区 |
| 21 | 丸子宿(まりこしゅく) | 静岡県静岡市駿河区 |
| 22 | 岡部宿(おかべしゅく) | 静岡県藤枝市 |
| 23 | 藤枝宿(ふじえだしゅく) | 静岡県藤枝市 |
| 24 | 島田宿(しまだしゅく) | 静岡県島田市 |
| 25 | 金谷宿(かなやしゅく) | 静岡県島田市 |
| 26 | 日坂宿(にっさかしゅく) | 静岡県掛川市 |
| 27 | 掛川宿(かけがわしゅく) | 静岡県掛川市 |
| 28 | 袋井宿(ふくろいしゅく) | 静岡県袋井市 |
| 29 | 見附宿(みつけしゅく) | 静岡県磐田市 |
| 30 | 浜松宿(はままつしゅく) | 静岡県浜松市中区 |
| 31 | 舞阪宿(まいさかしゅく) | 静岡県浜松市西区 |
| 32 | 新居宿(あらいしゅく) | 静岡県湖西市 |
| 33 | 白須賀宿(しらすかしゅく) | 静岡県湖西市 |
| 34 | 二川宿(ふたがわしゅく) | 愛知県豊橋市 |
| 35 | 吉田宿(よしだしゅく) | 愛知県豊橋市 |
| 36 | 御油宿(ごゆしゅく) | 愛知県豊川市 |
| 37 | 赤坂宿(あかさかしゅく) | 愛知県豊川市 |
| 38 | 藤川宿(ふじかわしゅく) | 愛知県岡崎市 |
| 39 | 岡崎宿(おかざきしゅく) | 愛知県岡崎市 |
| 40 | 池鯉鮒宿(ちりゅうしゅく) | 愛知県知立市 |
| 41 | 鳴海宿(なるみしゅく) | 愛知県名古屋市緑区 |
| 42 | 宮宿(みやしゅく) | 愛知県名古屋市熱田区 |
| 43 | 桑名宿(くわなしゅく) | 三重県桑名市 |
| 44 | 四日市宿(よっかいちしゅく) | 三重県四日市市 |
| 45 | 石薬師宿(いしやくししゅく) | 三重県鈴鹿市 |
| 46 | 庄野宿(しょうのしゅく) | 三重県鈴鹿市 |
| 47 | 亀山宿(かめやましゅく) | 三重県亀山市 |
| 48 | 関宿(せきしゅく) | 三重県亀山市(関町) |
| 49 | 坂下宿(さかしたしゅく) | 三重県亀山市(旧関町の一部) |
| 50 | 土山宿(つちやましゅく) | 滋賀県甲賀市土山町 |
| 51 | 水口宿(みなくちしゅく) | 滋賀県甲賀市水口町 |
| 52 | 石部宿(いしべしゅく) | 滋賀県湖南市石部 |
| 53 | 草津宿(くさつしゅく) | 滋賀県草津市 |
| 54 | 大津(おおつ) | 滋賀県大津市 |
| 55 到着点・京都 | 三条大橋 | 京都府京都市中京区(三条通) |
なんで55個も宿場町があるのに、“五十三次”って言うの?って思うかもしれないけど…
実は、“次(つぎ)”っていうのは、宿場と宿場のあいだの区間のことなんだ。
スタートの『日本橋(にほんばし)』と、ゴールの三条大橋(さんじょうおおはし)は、宿場町じゃなくて、出発点と到着点っていう扱いなんだよ。
だから、途中の53か所の宿場町だけをカウントして『五十三次』って言うんだって!
なんだかちょっと不思議だけど、昔の旅の数え方っておもしろいね。
東海道五十三次がちゃんと整備されたのは、1601年(慶長6年)のことだよ。
このころ、徳川家康(とくがわ いえやす)が全国をまとめて、江戸幕府をひらいた直後なんだ。
家康は、“江戸と京都を安全に行き来できるように”って、東海道を整備して、宿場町をつくったんだって。
それで、日本橋を出発して、京都・三条大橋までのあいだに、休める場所を53か所つくったわけなんだよ〜!
旅の安全のためにも、情報や荷物の伝達のためにも、すごく大事な道だったんだってさ。
東海道五十三次と歌川広重
東海道を旅するなら、外せないのが歌川広重の浮世絵だよ。
彼が描いた「東海道五十三次」は、江戸(東京日本橋)から京都(三条橋)までの道のりにある五十三の宿場町を、美しい風景や人々の暮らしとともに表した名作なんだ。
たとえば箱根の山道では、険しい峠を越える旅人たちの様子が力強く描かれてるし、庄野(しょうの)宿では、雨の中を急ぐ人々の姿がしっとりと描かれていて、まるでその場にいるみたいな気持ちになるんだよ。
おいらも、旅をするたびに「この風景、広重が描いてたなあ」なんて思い出して、ちょっと感慨深くなるんだ。
旅って、今も昔も、やっぱりいいもんだねぇ。